自動車保険の等級制度とは、ものすごくカンタンに言うと、事故歴に応じて保険料を割引きしたり、割増しする制度のことです。
保険料の割引率に応じてランクがあり、このランクを「等級」と呼びます。
※等級制度は正式には「ノンフリート等級別料率制度」と言います。
ノンフリートとは
所有する自動車が9台以下の場合の契約がノンフリート契約です。法人で10台以上の自動車を所有している場合の契約をフリート契約といいます。
本ページはプロモーションが含まれます
自動車保険には等級制度があり、等級が上がると保険料が安くなります。
最初は6等級からスタートするよ
家計内で何か少しでも節約できないかと生活費を見直ししている中で気気付いた「自動車保険料が高い」という事実。
この自動車保険料を見直して何とか安くできないか?と思い調べていたら、等級制度というものがあることを知りました。
この等級制度についてちょこっと知っておくだけで、自動車保険料の節約につながります。
等級って何?何段階あるの?等級が上がると保険料はどれくらい安くなるんだろう?
更新時に他の保険会社に乗り換えたらもっと安くできないだろうか?
備忘録として、まとめてみました。
自動車保険の等級制度とは、ものすごくカンタンに言うと、事故歴に応じて保険料を割引きしたり、割増しする制度のことです。
保険料の割引率に応じてランクがあり、このランクを「等級」と呼びます。
※等級制度は正式には「ノンフリート等級別料率制度」と言います。
ノンフリートとは
所有する自動車が9台以下の場合の契約がノンフリート契約です。法人で10台以上の自動車を所有している場合の契約をフリート契約といいます。
等級は1~20まで20段階。1年でひとつ等級が上がっていきます
等級は、1~20の20段階ランクがあります(一部の共済では上限が22等級まであるところも)。
初めて契約する時は、基本的に6等級からのスタートです。契約日からの1年間で保険を使った事故がなければ、翌年に等級が1つ上がります。
※2台目以降の車を新規で契約するときは7等級からのスタート
等級は高ければ高いほど割引率が大きくなり、保険料は安くなっていきます。
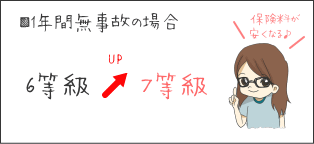
つまり無事故を続ければ(保険を使わなければ)保険料は年々安くなっていく、という仕組みになっています。
保険を使うとその代わりに等級がダウン!保険料が高くなる…!
事故を起こして保険を使った場合は、翌年の等級は下がり保険料が高くなります。
事故の種類によってどのくらい等級が下がるのかが決まり、最大で3等級も一気にランクが下がってしまいます。
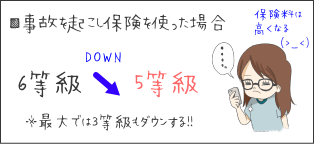
つまり…
事故に遭ったとき保険を使えば自費負担がない。だけどその代わりに等級が下がるから保険料が高くなる!
ということになるので、事故を起こしたときは保険を使うのか使わないのか、その後の等級ダウンによる保険料増も考えた上で、慎重に選択する必要があります。
| 1980年代半ば | 事故実績に基づいて無事故割引と事故割増の2種類で保険料が定められていた。 |
|---|---|
| 1984年 | これらを統合して、「ノンフリート等級別料率制度」ができる。 |
| 2011年10月 | 損害保険料率算出機構が改定案を金融庁に提出 |
| 2012年4月 | 等級制度導入(移行期間) |
| 2013年4月 | 等級制度導入 |
| 2013年10月 | 等級制度改定 |
年々、大手損保保険を中心にノンフリート等級制度は改定されています。
2011年10月に保険契約者間の公平性を確保するために、事故を起こして「保険を利用した人」と無事故で「保険を使わなかった人」を明確に分けよう、という改正案が持ち上がりました。
この結果、事故を起こした契約者は保険料が引き上げとなり、無事故の契約者は平均的に保険料が引き下げとなりました。
事故を起こした人は、3年間無事故の人とは別の料率表が適用されることに
それまでは同じ等級の人であれば、事故の有無に関わらず同じ割引率を適用していたため、事故のない人が事故ありの人の保険料を負担している状況でした。
新制度では事故の有無によって割引率を分け、同じ等級でも事故ありの人は3年間保険料が上げられることになりました。
さらに、車両盗難・飛び石・落書きなどの事故の場合、旧等級制度では、事故を起こしても等級は据え置いていましたが、今後事故を引き起すリスクが高いので翌年に1年間1等級ダウンへ変更されました。
この新制度は2012年4月1日から導入され始め、2013年4月1日から本格的に新ルールの適用が開始されています。
等級ごとの割引率は各社ほぼ同じ。SBI損保、全労済だけ若干違いが
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 割増 | 割引 | ||||||||||||||||||||
| 割引率 | 事故無 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 |
| 事故有 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
あいおいニッセイ同和損保、アクサダイレクト、共栄火災、セコム損保、損保ジャパン、東京海上日動、三井ダイレクト損保etc…多くの自動車保険の会社が上記の等級別割増引率表になっています。
SBI損保は若干割引率が異なり、12等級~19等級の割引率が上記の保険会社よりも低く、20等級では逆に他社より高い設定になっています。
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 割増 | 割引 | ||||||||||||||||||||
| 割引率 | 事故無 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 64 |
| 事故有 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
※全労災の自動車保険は、等級が22等級まであり、1等級は5つに区分されています。
(全労災の等級表はこちら)
等級は保険会社を変えても引き継ぐことができます
他の保険会社や共済に切り替えたとき、今まで積み上げてきた等級が下がってしまうのでは?と心配される方も多いと思います。
私も最初不安になったのですが、自動車保険は、等級を下げずに保険会社を変更することができます。
これは一般的に「等級の引継ぎ」と呼ばれています。
等級が引き継げるから、いつでも自動車保険会社を自由に選択できるよ
自動車保険の等級は、日本にある保険会社間すべての損害保険会社(一部の共済等は除く)の間で引継ぐことができます。
| メリット | ・等級が上がるほど保険料は減額される ・変更後も同様もしくは安い値段で支払いを続けられる |
|---|---|
| 注意点 | ・等級の引継ぎには条件がある ・親族でかつ同居しているなど、ある一定の条件を満たす必要がある |
上記の通り、等級を引き継ぐには条件があります。↓↓条件を詳しく見ていきましょう。
保険会社間だけでなく、配偶者や子供など
家族間でも等級の引継ぎができます
満期前に保険会社を変えずに車を乗り換える場合は、車両入替をします。
等級を引き継ぐには、以下の条件を満たしている必要があります。
上記2点のどちらかに当てはまり、等級を引き継ぐ人が下記の人であれば家族間で等級を引き継ぐことができます
子どもが新規で自動車保険の契約をすると、6等級からのスタートになります。
年齢が若く、さらに6等級だと自動車保険料がかなり高額になります。
(詳しくは→【自動車保険料の相場】年齢別保険料金相場一覧表)
この時親が20等級を持っていれば、その20等級を子供に引き継ぎ、親が6等級になることで2台分の車にかかる保険料を安く抑えることができます。
親子の等級を入れ替えるとトータル保険料が安くなります


親が新規で自動車保険へ加入すると6等級(もしくは7等級)からのスタートになりますが、ゴールド免許や年間走行距離、年齢が考慮され、子供が新規で契約した場合よりトータルで保険料を見ると安くなります。
同居している子どもにしか等級は引き継ぐことができないよ
子供は親族に含まれますが、等級継承制度はあくまで同居の子供が対象となります。
親元を離れる場合は、同居しているうちに等級の引継ぎをしておくのがポイントです。
満期前に等級の引継ぎをすると、等級アップが遠のく!
等級の引継ぎを上手に使えば節約になるのですが、注意しなければいけないことが1点あります。
それはなるべく満期が来る前には引継ぎはしないということです。
通常、等級は1年間無事故であれば1つ上がります。が、契約の満期でないとアップしません。
等級を継承した日が契約の始期になるので、等級が上がる前に引継ぎの手続きをしてしまうと、例えその間無事故であったとしても等級は上がらない、ということになります。
上手に等級を引き継ぐには、前の契約の満期日(解約日)、もしくは満期日(解約日)の翌日から起算して7日以内に手続きを済ませましょう。
できるのであれば保険期間中に変更をするのではなく、満期日をもって等級が引き継げるように事前に考えておくと節約につながります。
基本的に等級を引き継ぐ時の手続きは、名義を変更するだけで完了します。
名義変更の手続きに必要な書類は、自身で用意するものと保険会社から入手するものがあります。
車を乗り換えても等級はそのまま引き継ぐことができます
2台の自動車を所有していて等級を入れ替えたい場合、「契約済み」の自動車保険は等級の入れ替えができません。
たとえ契約者の同居の親族であっても、新規購入・譲渡・廃車を伴う時でなければ自動車保険の等級の入れ替えはできません。
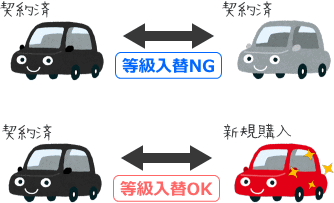
既に手元にある保険契約済みの2台の自動車の等級を入れ替えたい場合は、親の車を廃車にして親が新しい自動車に乗り換え、新規で保険に加入。そして、親の自動車の保険を子供の自動車の保険に入れ替えれば可能になります。
等級が下がるのはどんなとき?
事故を起こし保険を使うと等級が下がります。結果、保険料が高くなってしまいます。
「等級が下がるのはどんな時なんだろう?」
「もし等級が下がってしまったら、元の6等級にリセットできるのだろうか?」
そんな疑問を詳しく解説していきます。
事故を起こして保険を使った場合、次年度の等級は原則「3等級ダウン事故」となります。
ただし事故の状況によっては「1等級ダウン事故」や「ノーカウント事故」となる場合もあります。
事故の例を以下で紹介します。
※1等級ダウン事故やノーカウント事故に該当しないものは、すべて3等級ダウン事故になります
下がってしまった等級を、すぐにリセットできる制度は残念ながらありません・・・!
等級は1年間無事故で1等級ずつ上がるので、単純に3等級下がった場合は元に戻すのには3年掛かります。
下がってしまった等級を何とか6等級にリセットできないだろうか?と考えますが、残念ながら基本的に自動車保険は等級のリセットができません。
契約する保険会社を替えても、等級が再び新規6等級からスタートするわけではありません。
無事故を続けて得た高い等級が保険会社を替えても引き継がれるのと同様に、下がった等級もそのまま引き継がれます。
解約しても13か月の間はそのままの等級が残ってしまいます
自動車保険を一度解約して入りなおせば6等級からやり直せると考えるかもしれませんが、1~5等級の人は契約を解約しても13ヶ月間は等級が引き継がれることになっています。
これから運転しない人であれば、13カ月以上保険に加入しなければ等級がリセットされます。
保険を解約してから13ヶ月間は自動車保険の等級をいつでも再開することができます。
例えば妻が事故を起こし5等級以下に落ちてしまったとします。
そこで車を買い替えて夫の名義で自動車保険に新規加入すれば、また6等級からスタートできるのでは?と考える人もいると思います。
購入時に車の販売スタッフに交渉すれば6等級の加入が認められるケースもあるようですが、原則、同居家族で4等級の契約が直近1年以内にあれば、6等級からの新規加入は認められません。
事故を隠して許可を得ることなく6等級から契約できたとしても、後でバレたときに引き受け拒否の通知をされることがあります。
現在契約している自動車とは別に、新規でもう一台新規契約すると、セカンドカー割引制度が適用されて、2台目、3台目以降は、7等級から契約できます。
ただし、条件があり1台目の契約が11等級以上で契約されている場合に限ります。
中断制度を利用すれば、今の等級を10年間保存できる
車を廃車にしたり、転勤や海外留学などで暫くに車を乗らなくなるケースがあります。
そんな時は保険会社に「中断証明書」を発行してもらえば、再び自動車保険に加入した時に今の等級を引き継ぐことができます。
中断証明書を取得できれば、今の等級を10年間保存することができます。高い等級を持っている場合は一度契約を解約して新規契約するのではなく、中断制度を利用しましょう。
中断証明書を発行してもらうには一定の条件を満たしている必要があります。
解約日、または満期日までに契約車両が以下の条件に該当している必要があります。
もし6等級以下であれば、中断証明書を発行してもらうことはできません。契約を解約してから13か月以内であれば、現在の等級を引き継ぐことになります。
中断証明書を発行しない場合、13か月を超えますと、リセットされて、6等級からの契約になります。
※記名被保険者の配偶者・同居の親族は同一とみなされます。
等級が据え置きになる等級プロテクト特約は現在廃止されているよ
「等級プロテクト特約」とは、3等級ダウン事故を起こしても等級が下がらず据え置きになる特約です。
2012年4月にノンフリート等級制度が導入されて以来、共済や各保険会社は現在「等級プロテクト特約」を廃止しています。
この特約は、事故を起こし保険を使っても、年に1回までなら保険料増を気にすることなく保険を使えたので契約者にとってありがたい特約でした。
廃止の理由は、等級制度の改定によって等級据え置き事故の概念がなくなったことが挙げられます。
また、等級プロテクト特約を使えば等級が下がらないので、小さな事故でも保険金を請求する人が増えたことも理由のひとつです。
等級プロテクト特約は保険会社にとって赤字要因の一つで、等級制度改定をきっかけに現在どこの保険会社でも取り扱いがなくなりました。
自動車保険の一括見積りで保険料が54,500円→29,080円に!
25,420円安くなりました
複数の自動車保険会社の保険料を比較できる、「保険スクエアbang!」は、
大手損保複数社の見積りがリアルタイムで表示されるので、自分にとって1番安い自動車保険会社がすぐにわかります。

利用者数400万人以上と安心の実績があり、見積りは満期日の119日前(約4カ月前)から可能!
もちろん見積りは無料です。我が家もここで自動車保険料が25,420円も安くなり、家計が節約できました!
→無料一括見積りはここからできます。